冒頭の写真は我が家のリビング南面の様子です。窓を開け放つとこのような状態になります。・・・違和感がありませんか?窓らしきものがありませんよね。工事中の写真ではなく、今現在の様子です。庭のいろはモミジが紅葉しています。
春から秋にかけて、このように窓を開け放つと、ものすごく解放感があります。テラスにいるような雰囲気になり、気持ちいい風が抜けていきます。これを実現するための必須アイテムが木製サッシになります。
日本ではあまり使われなくなった木製サッシについて、メリット・デメリットを交えてお話したいと思います。ちなみに海外では現在でも主力サッシとして木製サッシが使われているようです。
木製サッシとは
窓枠部が木製のサッシのことです。既製品もありますが、我が家はオーダーメイドです。建築士と相談してデザインを決め、材木屋から木材を、ガラス屋からガラスを仕入れ、建具屋が加工して組立・取付を行いました。
木材やガラスの種類、鍵などの金具からデザインに至るまで自由にできるので逆に困りました。奇をてらわないオーソドックな感じにした結果、昭和な雰囲気の窓になりました笑。外壁材や床材と同様に、窓枠も無垢の木のままで無塗装としています。
木製サッシのメリット
- 木の特性で断熱性が高いため、窓枠部が結露しにくくなります。我が家ではガラス部を含めて結露したことはありません。
- 木製サッシの雰囲気は、和風にも洋風にも合わせやすく、存在感があると思います。
- 無垢の木であれば経年変化を楽しめます。
木製サッシのデメリット
- 通常のアルミサッシよりコストが高いです。
- 気密性の確保には工夫が必要です。
- 直接雨がかかると劣化が進行しやすく、後々のトラブルの元となり得ます。雨がかり対策やメンテナンス計画など事前準備が必要です。
木製サッシだから可能になるフルオープン
先ほどお見せしたリビング南面の開口部ですが、網戸を閉めるとこのようになります。3枚の網戸が確認できると思います。開口部が全て網戸になっています。

通常使われるアルミサッシでは、このようにフルオープン状態にすることや開口部全てを網戸にすることは困難です。例えば引違窓の場合、窓を開けると最大でも窓1枚分が開くことになります。網戸になるのも窓1枚分ですね。こちらは我が家の寝室の引違窓です。どうあがいても窓1枚分しか開きません。

木製サッシにするとなぜフルオープンにできるのか、答えは戸袋の中にサッシを引き込んでいるからです。木製サッシや網戸、雨戸はそれぞれ戸袋の中に仕舞うことができます。全てを戸袋の中に仕舞うと最初の写真のようなフルオープン状態になるのです。

窓がパズルに
この南面の開口部には、窓が3枚、網戸が3枚、雨戸が3枚の合計9枚あります。それぞれがレールの上を動き、隙間なく閉まり、使わない時は戸袋の中に仕舞うように計画する必要があります。
つまり、どのレールに何を配置して、どのように仕舞うかという問題を考えなければなりません。単純に1枚ごとに1本のレールを用意する手法がよく用いられますが、そうすると、合計9本のレールが必要になるので、この部分が外側に張り出していきコストが嵩みます。

引用:有限会社こころ木造建築研究所 ―職人の手仕事でつくる木の家 静岡市 藤枝市 島田市―
我が家では、コスト面・デザイン面から、レールの本数を最小化するという条件も追加して、レールを何本にして、どのレールに何を配置して、どのように仕舞うかという問題を考えました。中々難しいパズルでしたが、最終的にレール本数は3本にしました。次のように4つのモードがあります。
① 全開モード
イメージを掴むために模式図を描きました。スケールが少しおかしいですが、サッシの部分を真上から見た図です。上側が室外、下側が室内です。左右にある橙色の箱が戸袋、破線がレールです。
全開モードでは、サッシ(青色)、網戸(灰色)、雨戸(橙色)が戸袋内に仕舞われています。サッシはレールを2本使い、その内1本のレールは2枚のサッシで共用し、サッシ同士がぶつからないように、左右の戸袋を使い分けて仕舞います。

② 網戸モード
一番外側のレールは網戸と雨戸で共用します。網戸モードは以下のようになります。網戸の役目は、室内に虫が入ってこないようにすることなので、隙間があっては意味がありません。我が家の場合、網戸と戸袋の接点で隙間を無くしています。

③ 通常モード
網戸とサッシを閉めたこの状態が通常モードです。

外から見るとこんな感じです。網戸には目隠しの役目もあります。

網戸が無ければこんな感じです。

南面の統一感を出すため、リビング横の和室にも木製サッシを採用しています。こちらはサッシ、網戸、雨戸が2枚ずつですが、リビングと同様に戸袋に仕舞うことができます。カーテンではなく、障子が見えていい感じです。こちらは完工時の写真なので、風合いが違います。白い肌!

ちなみに玄関の扉も木製オーダーメイドの引戸です。引戸の後ろには網戸も用意しています。こちらは最近の写真で早くもクリスマスモードです。それにしても完工後3年で結構風合いが変わるものですね。

④ 雨戸モード
使用頻度は低いですが、台風などの暴風雨の時や、ものすごく寒い冬の日には雨戸を閉めます。この時は網戸が戸袋に仕舞われて、雨戸が出てきます。

外から見るとこんな感じです。普段は戸袋に仕舞われているので、外壁やウッドデッキと経年変化の度合いが全然違います。

木製サッシのコスト
我が家の木製サッシのコストを見てみます。網戸や雨戸も含めています。上段はリビング、下段は和室のコストです。2か所で約50万円・・・なかなかのお値段かもしれません。なお、サッシ1枚の寸法は約2,000mm x 950mmです。
リビングの木製サッシコスト
| 所掌 | 項目 | 税抜単価 | 数量 | 税抜金額 |
|---|---|---|---|---|
| 材木屋 | 窓枠(杉) | 23,700 | 3 | 71,100 |
| 材木屋 | 網戸枠(杉) | 8,130 | 3 | 24,390 |
| 材木屋 | 雨戸(杉) | 10,647 | 3 | 31,941 |
| ガラス屋 | 複層ガラス | 20,145 | 3 | 60,435 |
| 建具屋 | サッシ加工 | 12,000 | 3 | 36,000 |
| 建具屋 | 網戸加工 | 8,000 | 3 | 24,000 |
| 建具屋 | 雨戸加工 | 14,000 | 3 | 42,000 |
| 合計 | 289,866 | |||
和室の木製サッシコスト
| 所掌 | 項目 | 税抜単価 | 数量 | 税抜金額 |
|---|---|---|---|---|
| 材木屋 | 窓枠(杉) | 23,700 | 2 | 47,400 |
| 材木屋 | 網戸枠(杉) | 5,420 | 2 | 10,840 |
| 材木屋 | 雨戸(杉) | 10,800 | 2 | 21,600 |
| ガラス屋 | 複層ガラス | 20,010 | 2 | 40,020 |
| 建具屋 | サッシ加工 | 12,000 | 2 | 24,000 |
| 建具屋 | 網戸加工 | 8,000 | 2 | 16,000 |
| 建具屋 | 雨戸加工 | 14,000 | 2 | 28,000 |
| 合計 | 187,860 | |||
和室のサッシについては、アルミサッシでも見積を取っており、窓2枚+網戸1枚で合計110,080円でした。雨戸のコストを除いた木製サッシのコスト(138,260円)とアルミサッシの見積金額を比較すると約25%木製サッシの方が高いということになりました。
おまけ
少し話が脱線しますが、我が家は尺モジュールで建てているので、柱が大体910mmピッチで配置されています(柱の中心間の距離が910mm)。また、我が家の構造は伝統工法というお話をしました。
通し柱と呼ばれる柱(1階から2階の屋根まで突き抜ける柱)が所々にあるのですが、
通常の柱(1階と2階の間のみにある柱)と太さがかなり異なります。我が家の通常の柱は4寸(約120mm)、通し柱は7寸(約210mm)という感じです。
例えば、窓の片側が通し柱で反対側が通常の柱にかかる場合など、既製品の窓のサイズが合わない場所が出てきます。その場合、アルミサッシであったとしても特注になり、余計なコストが発生しました。


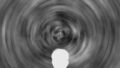

コメント